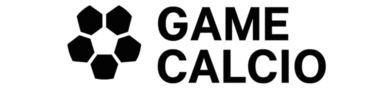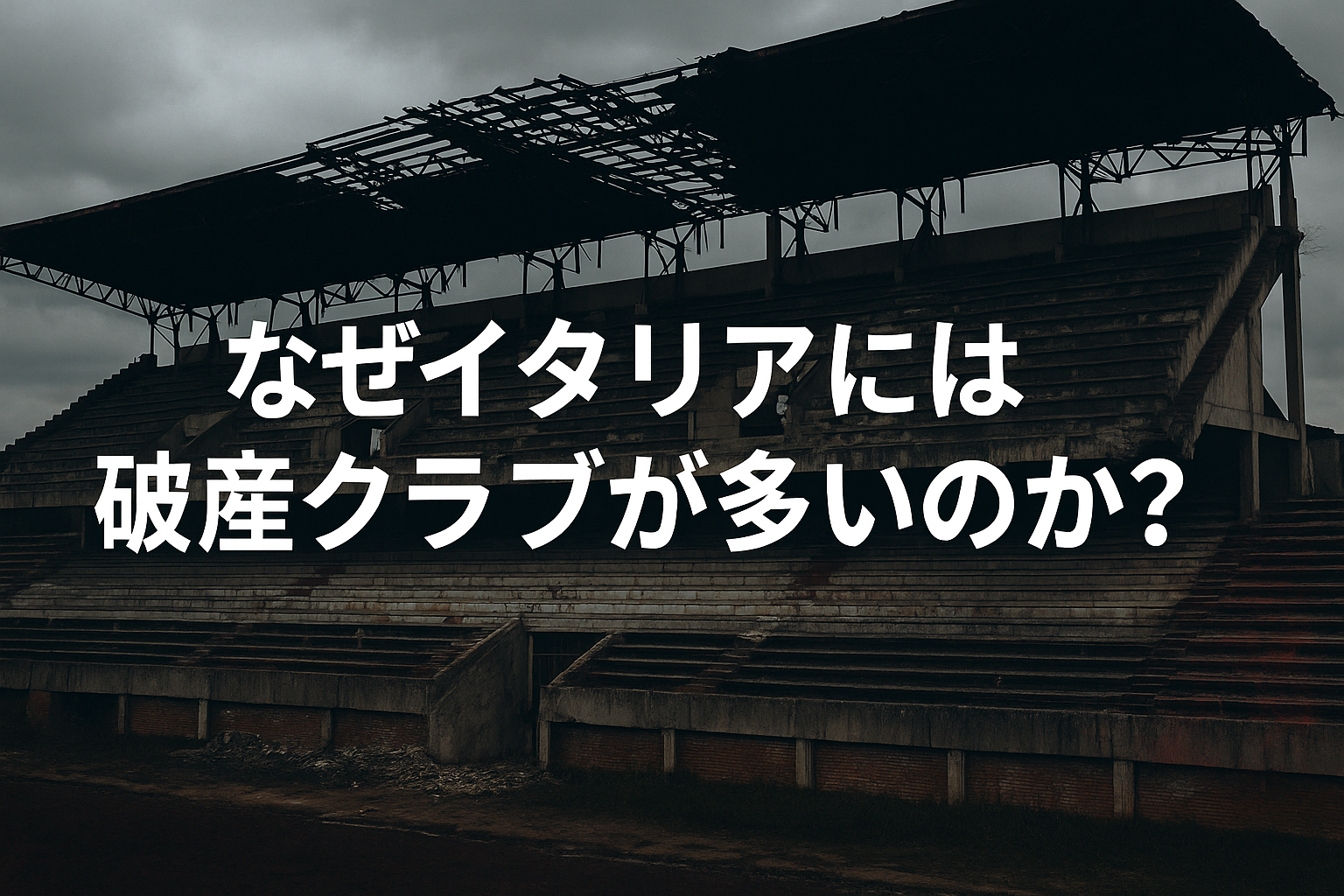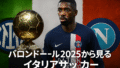はじめに:破産クラブの異常な多さ
名門クラブにも関わらず、イタリア・セリエA/Bには 破産経験・経営破綻経験 を持つクラブが複数存在します。
ブレシア、パルマ、さらにはフィオレンティーナやナポリも、かつて深刻な財政難や再建を経験しました。
なぜ歴史あるクラブでさえ“破産の危機”が現実となるのか。
本稿では、その根本原因と、さらには現在のセリエAが抱えるブランド衰退の背景に迫ります。
イタリアで破産クラブが多い主な理由
1. 放映権収入の偏在
最も根源的な問題の一つが、放映権収入の不均衡です。
ユヴェントス、インテル、ACミランといった“ビッグクラブ”が収益の大部分を占める構造になっており、地方クラブ・中小クラブには十分な配分が回ってきません。
この点で、イングランド・プレミアリーグのような「均等分配モデル」との対照性が際立ちます。
例えば、ビッグクラブが国際大会によって得る放映権料や広告収入は桁違いであり、リーグ内での格差が拡大していきます。
一方で中小クラブは、試合数・放映契約数が限られているため、収益基盤が脆弱になります。
2. オーナー依存と経営の脆弱性
イタリアの多くのクラブは、富裕な実業家や地元企業の資金支援に依存しています。
そのため、オーナーの経済情勢・親会社の事情がクラブ経営に直結します。
たとえば、パルマはかつて乳製品メーカー「パルマラット」が親会社であり、その破綻がクラブ財政へ悪影響を及ぼし、2004年に一度破産を経験しました。
また2015年には再び経営破綻し、セリエDからの再出発を余儀なくされた歴史があります。
このように、オーナー基盤が不安定であると、成績重視の方針が無理なビジネス拡大や債務拡大を招き、クラブが破綻へのスパイラルに入ることがあります。
3. インフラ問題(スタジアム)
スタジアムを自前で所有していないクラブが多く、自治体所有や古い施設を借りているケースが多いです。
これにより、スタジアム改修・収益化(飲食・ショップ・イベント利用など)が難しく、クラブが収入を最大化できない要因となります。
唯一、ユヴェントスが自前スタジアムを持ち、商業展開を進めて成功している例が、逆にこの構造問題を浮き彫りにしています。
4. 財政管理と “勝利至上主義”
クラブは「今シーズンで勝つ」「上位に上がる」という目先の成績を追い求めがちです。
それゆえに、無理な補強や高額契約を重ね、短期成果を狙ってキャッシュフローを圧迫する流れが生まれます。
また、会計の透明性が低いクラブもあり、不正会計・脱税・費用隠蔽のスキャンダルが表面化することもあります。
このような経営スタンスの甘さが、破産リスクを高める要因としてしばしば指摘されます。
事例で見る「破産クラブ」
パルマ
- 1990年代には欧州舞台で躍進した名門
- 2004年:親会社破綻が引き金となりクラブも財政破綻
- 2015年:再び破産し、セリエDからの再出発
- 歴史あるクラブが、クラブとしてのブランドとファン基盤を失わずに再建を図った例でもあります
ブレシア
- 日本のサッカーファンにもなじみ深いクラブ(バッジョやピルロを輩出)
- 昇降格を繰り返す中で経営が不安定
- 施設投資不足や資金難による経営危機を何度も経験
- 中小クラブが抱える典型的な課題を体現しているクラブです
これらのケースは単なる失敗ではなく、構造的な問題が重なった結果と言えるでしょう。
なぜセリエAはブランド力を維持できないのか?
破産クラブが多い背景と併せて、セリエA全体のブランド力低下についても見ておきましょう。
1. プレミア・ラ・リーガとの格差
英プレミアリーグは世界的なマーケティング力と放映権戦略で強固な地位を築き、スペインのラ・リーガもメッシやロナウドといったスター選手時代の拡張で国際的影響力を拡大してきました。
対照的に、セリエAはスター選手の流出が続き、「世界最高リーグ」の冠を維持する磁力を失ってきた感があります。
2. 国際大会での影響力低下
過去にはセリエAクラブが CL/EL で優勝する機会も多く、イタリアリーグの威信を支えていました。
しかし近年はその勝ち星が減少し、国際成績での存在感が弱まりつつあります。
この点がブランド力の希薄化に繋がっています。
3. 経済基盤の弱さ
放映権料、スポンサー収入、商業収入のすべてが、主要リーグに比べて低水準です。
そのためクラブは経営難のリスクを抱えやすく、外資導入も難しいという現実があります。
4. スタジアムと観客体験の問題
老朽化したスタジアム、施設の不備、観客快適性の低さが、観戦動機を下げています。
一方で、他リーグは最新施設や観客体験(VR体験、商業施設併設など)を重視しており、差が開いています。
5. マーケティングとグローバル展開の不足
SNS や動画配信、国際的なファンコミュニティ形成の遅れも響いています。
若年層への訴求力やファン拡大力が不足しており、リーグ全体の存在感が希薄になってしまっているのです。
今後の課題と展望
セリエA・イタリアサッカーが再び輝きを取り戻すためには、以下の点が不可欠だと考えられます:
収益分配モデルの見直し
プレミア式の公平分配モデルを導入し、リーグ全体の安定性を高めることが求められます。
スタジアム近代化・観客体験の強化
クラブが自前スタジアムを持つこと、商業併設とブランド体験強化が鍵。
若手育成・スター定着
育成システムの強化と選手の流出防止、さらにはバロンドール級スターを生む環境づくり。
グローバル戦略とブランディング
SNS戦略・国際放映展開・ファンエンゲージメントの強化に注力し、ブランド再建を図るべきです。
まとめ
- ブレシア・パルマの破産事例は、クラブ単体の問題ではなく、構造的課題の象徴
- 放映権の偏在、オーナー依存、スタジアムインフラ、勝利至上主義などが複雑に絡み合う
- セリエAは依然魅力的なリーグながら、ブランド力が弱まりつつある現実
- ブランド再生には、クラブ運営・育成体制・観客体験・国際戦略の総合強化が不可欠
「なぜイタリアには破産クラブが多いのか?」という問いは、単なる過去の話ではなく、セリエAの未来を語るテーマでもあります。
クラブもファンも、リーグがもう一度、世界最高峰に返り咲く日を目指して、変革の時を迎えています。